これはガストロノミー界において、最も精巧な弱点の一つであるに違いない。
コピー品。
本物より強い印象をうけかねない。
「舌平目の柑橘風味」が、抜け目のないレストランのメニューに登場したかと思うと、翌日の朝には、すべてのライバルレストランで、その料理が味わえたりする。
この現状は、小規模なレストランにおいてだけではなく、高級レストランにおいても変わらない。
マグロのフォアグラ添え、かりかりのラングスティン、オマールのバニラ風味。
これらの料理は、まずくはないリフレインといえるが、どこかに端かゆい印象が残る。
デュカスのもとで修行した、神秘的なシェフ、ジャック・マキシマンはこういった。
「創るということは、コピーすることではない」
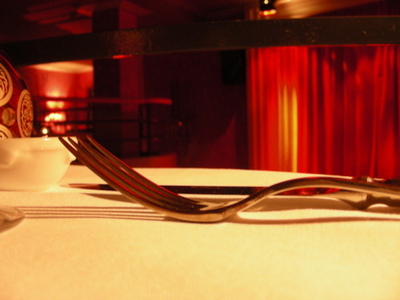
ペテン師たちは、この話をよく心得ている。
というのも、フランス人シェフたちが一番この傾向にあるらしいからだ。
なぜコピー品がうまれるのか。
そのもっとも大きな原因は、恐怖感だ。
他との差異(いや無感覚)の中に自分を見つけるのに恐れをなし、他人と一緒にいないことに震え上がる。
だから、似たような料理を作ってしまう。スプマンテ、窒素、グラス盛り、ペピット、タガダのイチゴ菓子等々。
フランスのレストラン料理が、どこもにたようなものになってくるわけだ。
明け方に、いたずら好きが、火花しかみえない高級レストランのメニューをすれ変えにいったらおもしろいかもしれない。
そんなわけで、我らの素晴らしいガストロノミーは、他国の料理が差異の中を飛び回り、光きらめいている一方で、ぶるんぶるん鳴ってでこぼこ道を突っ走り、独り言をぶつぶつ唱え続ける。
アイデアがいいと、いつもその影に「僕にもできるぞ」と思い込む人間が存在する。
これがあの「me too」現象だ。
例は多々ある。
エディション・ド・レピュールの小さな本は、マラブーがコピーした。
アレクサンドル・カマスとエマニュエル・リュバンによって開始されたフーディングは、 特許までとっているのに、フルリー・ミションの「フーディング・タンタシオン」シリーズのコピー品だと、ペテンにかけられた。正当っぽい理由から判決は下り、そしてそれが間違いだとなると、話は上告に進むだろう。前回の判決では、この言葉が一般用語だと判断され、工業グループが勝利をあげた。
この話は、エゴと大金のありふれた話でありえたが、そうではなかった。
寒さに凍え2つ折りになった我々のガストロノミーの前兆だったのだ。
違う言葉、違う料理、違うリスクへと扉をひらくために、このスパイラルダンスから抜け出すときがきたのかもしれない。
マーケティングの侯爵たちに、アングロサクソン系の言葉を使うことが新しいことなのだと思いこませることをやめ、フランス用語辞典を開いて、新鮮で詩的で革新的な空間が僕らの手の中に隠されていることを、伝えよう。
もうあと一息だ。

コメント