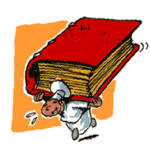![]()
シェフが突然、メニューの上で「食材の真実」を語ることは、笑えるくらいに厚かましいことだ。
今日「真実」は雲行きの悪い時代を生きている。
性別を変えて、無限に続くエコーの中で、歪曲してしまった。
それはパリの豪華パラスレストランで食べた、感心さえできる、窮屈そうなラングスティンがその一例だった。
裸の料理、すべてが取り除かれて一つの音声しか聞こえない、まるでアカペラみたいな料理は、少し時代をさかのぼるレストランで味わえる。
たとえば、クロード・ペイロのヴィヴァロワ Vivarois、ベルナール・パコーのランブロワジー l’Ambroisie、そしてラストゥールにあるジャン=マルク・ボワイエのピュイ・デュ・トレゾー Le Puits de Trésor がそのジャンルに入る。
彼は、パコー出身で、ヴィヴァロワでも研修を受けている。
彼が、野うさぎのセップ茸添えを仕上げる時、皿の上には何も余分なものをのせない。
半生の切り口が朝日の優しさを語るセップ茸は、手で丁寧に積まれたに違いないし、野うさぎはさっきまで近くの荒地で跳ね回っていたことだろう。
セロリーのピューレがそれに付き添う。
この料理は本当にシンプルで、ジョゼフ・デルティユの本の中に迷い込んだ気分に陥った。(La Belle Aude – Edition Collot)
これらすべての努力の傑作に、「お見事!」と声を上げたくなる瞬間が訪れる。
後ろを省みずに前線へひとり突っ走り、情熱に胸を駆り立てられながらも、極悪の「真実」を前に、孤独を噛み締めるには、少々勇敢でなければならない。
オマールのフリカッセ、かりかりのパスタ添え。カエルのもも肉のフリット。仔羊の背肉。
その夜は、オーブ県のド田舎のレストランで、うまくて骨格のはっきりしたその地方のワインと、幸せそうな客層に囲まれて、完全降伏の幸福を味わった。
Le Puits de Trésor
T. 04 64 77 50 24
コースが39ユーロから
www.lepuitsdutresor.com