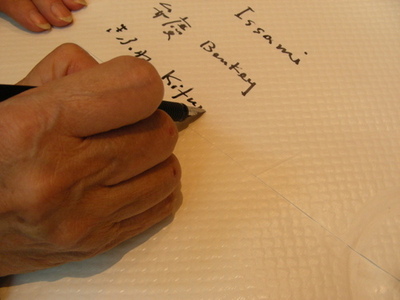はっきり言って、こんな話を記事にするのはまっぴらだ。
ティエリー・マルクスのレストラン、シャトー・コルディヨン・バージュは、誰もが一度は耳にしたことがあるだろう。
マスコミは、彼の最高のイメージを大きく映し出す。
すごく感じがよくて、どこか遠くからやってきたタイプ。世界中を駆け巡ったその経歴は、誰もが彼を尊敬してしまうだろう。どのガイドブックを開いても、このスーパーシェフを表現する言葉は全会一致だ。
いい面、切れる頭の持ち主、モダン、柔軟性がよく、控えめで正直。

だから、彼のレストランを訪ねて唯一期待することといったら、これらのガイドブックの好意的な批評に、自分も一票入れることだろう。
かごの中で身を丸める子猫みたいに、体をなめまわして眠りに入りたい。
予約はずいぶん前から入れるはめになった。
ずーっと先まで毎晩満席で、ようやく平日のランチに予約が取れたのだ。
結果からしてみると、平日のランチも悪くないかもしれない。解放された時間を味わうことができて、頭もすっきりしている。
若々しくて、よく気の利くサービス陣。気合いの入ったその仕事ぶりから、彼らの情熱が、こっちにまで伝わってくる。
客層も悪くはない。
実は、レストランで偶然空間を共にする他の客達も、重要だったりする。
大声で叫んだり、行儀が悪かったり、無関心だったりして、こっちにまで被害を受けかねないからだ。そして一方では、気前のいい観客のおかげでシェフを大スターに持ち上げることもできる。そして、料理の方は、食欲が究極に高まったところで、シェフまでそれに影響されて、皿の上にその熱狂が伝達する。
初めに、前菜のなかで一番安い、29ユーロのパルメザンとグリーンピースの小さな一皿を頼んだ。温度の変化が微妙にすごくて、感情は頂点に達しかけていた。
しかし、エリートにしかわからない省略法で操られたアミューズ・ブッシュの連続は(すずめの涙ほどのキャラメルの中にビーツのジュレを挿入できる技巧!)、まるでありの合唱団の演奏を鑑賞しているみたいだった。
つまり、究極に整った、象みたいに巨大な聴覚、山猫みたいに鋭敏な視角を持っていなければならない。
個人的に、僕にはできない。
僕らはみんな、同じ大きさの口を持っていると思う。
ごく少量の更に少量は、この場に適した量ではない。一口食ならまだしも、切手くらい薄い厚さの、爪の白い部分より小さい料理なんて、信じられない。
前菜が出されたときには、食欲が怖じ気づいて、レストランを千鳥足で逃げまわり、暗闇の中を手探りで進んだ。(すでにシェフは気づいていたかもしれない)
そんなこんなで、6分ごとに額を走る汗の拷問に、シェフは少し狂気になって、救いの場所や隠れ穴をを探し始めた。そして、パンやバターや水のサービスで、僕も少し持ち直す。
一般食の4分の1の量の料理は、悪くはないが、驚くべき衝撃も受けるわけではない。
その上、シェフは抽象のなかに逃げ腰になってしまっていた。プライベートクラブに参加したいのに、ドアの覗き穴から見るだけでおしまい、という感じ。
しかし “石器時代のすずき、カカオ風味”は、すごかった。
普段は劇団で演じているだろうセミ女優っぽいウエイトレスが、粘土質の物体に木槌をふるい落としたときには、レストラン中の人が振り返ったに違いない。45%のカカオ風味のすずきの中に閉じ込められているものを想像するだけで、よだれがでる。しかし、いったんそれを口に入れてみたら、つまらなくはないが少し乾いていて、なんだか脳みそをよく動かさなきゃいけないけれど、食欲のほうはその正反対という印象を受けた。
脳みそは、食べ物、つまり料理が載った皿とのダイレクトなコンタクト、そしてなにか印象に残るものを欲している。
食欲にしてもそうだ。
だから、デザートのカヌレがでてきたときには、身を乗り出して食いついてしまった。(これはプレデザートだったんだけど)しかし、このカヌレは、フランス語が通じるのか疑ってしまう代物だった。「ウィ」と、ボルドーなまりの返事をしてきたから、その腰に縛りついて、一息入れたんだけど。
牛乳発酵の味がする生のブリオッシュは、興味深かったが、こういう表現は、どう感想を述べたらわからからないときに述べる意見だろう。
まぁ、こういう状況におちいったんだから、こんな表現も有効利用しようじゃない。
こんな体験を記事にしなければならないという運命。
僕のこのかわいい不理解を共有してくれる小多数派の美食家の為に、今回も思い切ったというわけだ。
PHOTO / F.SIMON